
映画『ファインディング・ニモ』あらすじ・動画
映画『ファインディング・ニモ』あらすじ
~あらすじ~
アカデミー賞長編アニメーション作品賞を受賞した魚の親子の絆を描く感動アニメ。元気で好奇心いっぱい、カクレクマノミの子供ニモは、初登校に大喜び。でも、ニモは同級生たちに度胸のあるところを見せようと、心配性の父マーリンの制止を振り切ってサンゴ礁の外に出たことから人間にさらわれてしまいます。
マーリンは、“ニモをさらったボートを見た”と言う、親切だけど物忘れのひどいドリー(ナンヨウハギ)を相棒に、ニモを探す果てしない海の旅へ―。巨大なサメに追いかけられたり、アオウミガメの群れに助けられたりと、想像もしなかった出来事ばかり。それでも、マーリンはニモに会いたい一心で旅を続けるのです。
出典:楽天TV
映画『ファインディング・ニモ』予告動画
\『ファインディング・ニモ』を宅配レンタル
<TSUTAYA DISCAS>で借りてみる!/
『ファインディング・ニモ』のキャラクターから、何を学んだのか
『ファインディング・ニモ』は作品自体がシンプルにできているうえに、持ち合わせるテーマ―を考えてみると、4や5つはあるのではないでしょうか?
私はTSUTAYAでバイト経験もしました。それ以外にも、学生ボランティアやゼミを通して「福祉」「社会保障」なども学んでいました。社会人になって、仕事柄も福祉系に携わっていました。
私の考えるテーマは「ハンディギャップ」「冒険」「勇気」「自然共生」、そして「愛情」の5つかな、と考えます。
「ハンディギャップ」
| キャラクター | 性格や特性 |
| マーリン | ニモの父親で超心配性のため過保護とも(シングルファーザー) |
| ニモ | マーリンの息子。後天的ハンディギャップあり(片ヒレが小さい) |
| ドリー | マーリンの相棒に。物忘れや言動に特性あるが、プラス思考である |
| ギル | 水槽の中のリーダー的存在。後天的ハンディギャップあり(魚体に傷) |
この広大な海のなかで、そして水槽のなかで「ハンディギャップ」までも描いた作品、アプローチしている作品は、アニメのなかでは観たことが無いのかもしれません。割かしアニメを観る機会が少ないからかもしれませんが・・・・。
なので、正直驚きました。
子・ニモは生まれた時に片ヒレが小さく(先天的な障害)、水槽のタンク・ギャング、リーダー的な存在であるギルも、落とされて負ったとされる傷(後天的な障害)があります。
また父・マーリンにしても、シングルファーザーで極度の心配性。
ニモ探しの際に相棒となったドリーも健忘症のようで物忘れ。何の義理も無いけれど、手助けがしたくてどこかうずうずしている・・・。面白いのですけど、言動も気になりました。
例え仕事柄も福祉系していても、「このような事が出てくる」といったことを何らかの機会、説明や形にしてもらわないと、察するにしても、周りのほうもどう対応したらよいか、戸惑ってしまいますね。
見えるハンディギャップ、見えないハンディギャップがあることも、お忘れなく。
アニメの世界だったから良かったのか。いや、そうでもない。
どうでしょうかね。
『ファインディング・ニモ』が公開されてから十数年の年月が経ちました。私たちが生きている社会はどう変化したのでしょうか。
ハンディギャップへの社会的認識は、少々たりとも認識されてきたのかなとも感じます。それでもまだまだ見えない壁はありますね。
作品の最後のシーンに差し掛かった頃、父・マーリンは子・ニモの生まれつきである小さなヒレを「幸運のヒレ」と名づけて賞賛し、互いに握手します。
マーリンとニモは、改めて親子として絆を、互いを認め合うことができたのです。父親としての優しさも感じましたね。
ハンディギャップは”個性”と言えばそうであるし、そうとも言えない。父・マーリンも、ニモ自身もハンディギャップがあることは、十分に認識しています。
ハンディギャップっていうのは、先天的、後天的であろうが、「なかなか自分のなかでは受入れがたい」ものがあります。
でも自分がどうしたいのか(どうすべきなのか)ということを悩み、考え、行動していくには「時間」というものが、絶対必要なのです。
頑に受入れられることができずに、迷ってしまうことも。
もしああなたが「いつまでも若い」とか絶対に「安心」「安全」など言っている方は、ちょっとくらい構えておく必要はありますね。いつ何時どうなるか分かりませんから。
健康であるのが一番良いのですが、ギルのように、後天的にハンディギャップを負う事だって、年齢を重ねることでなることだって、いくらでもありますからね。
「ハンディギャップ」は、本人や家族、会社そして取り巻く社会に国と、生活水準、社会活動への参加、社会的評価など多岐に渡るため、難しい問題ではあります。
「冒険」

あまりにも臆病で、心配しすぎる父・マーリンから離れたいと、子・ニモはダイビングをしていた歯科医につかまってしまいます。そしてマーリンはニモを探すための、大冒険がはじまります。
その距離は300kmあまり。シドニーまで・・・。途中、亀の群生(クラッシュやスクワート)に出会い!?オーストラリア東海流を回遊するシーンは好きだな。
一方のニモも、水槽のなかのキャラクターたちと共生しながらも、何とかかして水槽から脱しようとします。
ひとりの力では何もできないかもしれないけれども、周りの協力を得ながら、試行(思考)しつつ脱する機会をうかがっているのでした。
そして私たちには、この広大な海には未だ知られていない魚たちが住んでいることを知らされましたし、身近かな魚たちをしるためにも水族館に行ってみたり、海に行って魚を探してみる、何かを与えてくれたのではないでしょうか。
\『ファインディング・ニモ』を
宅配レンタル<TSUTAYA DISCAS>で借りてみる!/
「勇気」
聞き慣れた諺(ことわざ)を一言で言うと、「可愛い子には旅をさせよ」とうことなのでしょう。
可愛い子はニモかもしれませんが、実は父・マーリンにも相通じるものがあります。
子・ニモは、学校の友達でタツノオトシゴのシェルドンのひと声「安全なサンゴ礁から外に出て行こう!」と父・マーリンの静止を振り切ってサンゴ礁を出て行ったのですから!
私はむしろ、父・マーリンのほうが心配でなりませんでした。
スト―リー冒頭から、
・「もうお前には何も起こらないようにするよ」
・(エイ先生に)「うちの子は片ヒレが小さいので、うまく泳げないんです。よろしくお願いします」と。
ハンディギャップを持ったニモではあるけれど、臆病で心配症な父・マーリンだから、そうなってしまうかなと。
子・ニモ探しに、海の中にはさまざまな魚たちが住んでいるのでしょう。相棒で一緒に同行してくれるドリーとともに、様々ン魚たちに出会うことで、マーリンのなかにあるトラウマや心配症を克服していくことに、「成長していく感」というのを覚えました。
私は子どものニモというよりは、父親のほうの「ドリーの成長物語」かなと感じました。
「自然共生」
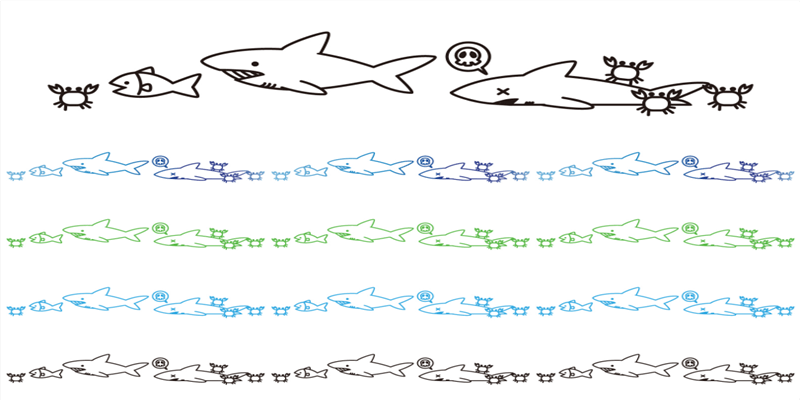
2時間という作品のなかにどれだけの魚たちや鳥、そして人が出てきたでしょうか。
海のなかには、もっと怖い魚たちがいます。
海にも「弱肉強食」で成り立ち、毅然とした「食物連鎖」というのが存在します。
本来なら、鯨やサメといった魚たちがピラミッドの頂点や2番手に立つものです。「大魚が小魚を食する」のでしょうが、作品のなかでは皆無ですね。
3匹のサメ(ホホジロザメ、シュモクザメ、アオザメ)が出てきましたが、菜食主義者で「お友だちつくろうキャンペーン」って(笑)
「弱肉強食」「食物連鎖」というところは、緩めに描かれているのはどうしようもないところです。
私がこの「自然共生」を思い浮かべたのは、昨今のサンゴ礁の減少や石灰化問題、本来いるべきであろう魚の生態系が変化していること(漁獲量の減少やいない海域に魚がいたりするなど)、温暖化の進行などで確実に海も変化しているなと、つくづく感じているからです。
映画『ファインディング・ニモ』無料視聴する方法と配信サービス
映画『ファインディング・ニモ』無料視聴する方法
以下の動画配信サービスで映画『ファインディング・ニモ』が見ることができます。
・ディズニー・プラス
では、見放題です。
宅配レンタルで映画『ファインディング・ニモ』が見ることができるのは、TSUTAYA DISCAS、DMM 宅配レンタル、ゲオ宅配レンタルです。
DISCASの「定額レンタル8」のプランの場合、月間レンタル可能枚数終了後は「旧作のみ借り放題」となります。
・Amazonプライム
・music.jp
・TELASA
・DMM TV
は、下記にある月額料金とは別に、個別課金「レンタル」が発生します。
映画『ファインディング・ニモ』配信サービス状況
| 配信状況: ◎見放題 〇レンタル ×未配信 | |||
| 動画配信サービス | 配信 状況 | 月額料金(税込)/初回・無料期間 | ⇒【公式】サイトへ無料登録する! |
 ABEMAプレミアム ABEMAプレミアム | × | 960円/無し | ⇒オリジナルコンテンツ番組ならABEMA |
 Amazonプライム | ○ | 600円/30日間 | ⇒Amazonプライムに申し込む |
 TSUTAYA DISCAS TSUTAYA DISCAS | ○ | 2,200円/30日間 ※定額レンタル8ダブルの場合。 | ⇒DVDレンタルするなら |
 music.jp music.jp | ○ | 1,958円/30日間 ※「music.jp 1780コース」のみお試しあり。 | ⇒30日間お試し!music.jp公式 |
 Leminoプレミアム Leminoプレミアム | × | 990円/30日間 | ⇒[初回初月無料]人気の映画・ドラマ・韓流作品・スポーツや音楽ライブの生配信・オリジナル作品の全話など、ここでしか見られないコンテンツが月額990円(税込)で見放題♪(※一部個別課金コンテンツあり) |
 TELASA TELASA | ○ | 618円/15日間 | ⇒TELASA(テラサ) |
 Netflix Netflix | × | 広告つきベーシックプラン790円~プレミアム1,980円/無し | ⇒Netflix |
 Hulu Hulu | × | 1,026円/無し | ⇒hulu |
 FOD PREMIUM FOD PREMIUM | × | 976円/2週間 | ⇒【フジテレビオンデマンド】 |
 U-NEXT U-NEXT | × | 2,189円/31日間 | ⇒U-NEXT |
 DAZN DAZN | × | STANDARDプラン:4,200円、GLOBALプラン:980円/無し | ⇒DAZN(ダゾーン) |
 dアニメストア dアニメストア | × | 550円/31日間 | ⇒dアニメストア |
 ディズニープラス ディズニープラス | × | 「スタンダードプラン」990円、「プレミアムプラン」1320円/無し | ⇒ディズニープラス |
 DMM TV DMM TV | ○ | 550円/14日間 | ⇒DMMプレミアム |
 DVD・CDレンタル [ぽすれん] DVD・CDレンタル [ぽすれん] | ○ | 2,046円/1ヶ月 ※「スタンダード8コース」の場合 | ⇒ネットで気軽にDVD・CDレンタル [ぽすれん] |
 ゲオ宅配レンタル ゲオ宅配レンタル | ○ | 2,046円/30日間 ※月額コース「スタンダード8」の場合 | ⇒今なら無料でお試し!「ゲオ宅配レンタル」 |
※本作品の配信情報は2023年8月8日時点のものです。
配信が終了している、または見放題/レンタルが終了している可能性がございますので、配信状況については、各動画配信サイト/アプリにてご確認ください。
※表示は税込。
※Amazonプライム→年額5,900円(税込)払いなら、月額換算で492円。
\『ファインディング・ニモ』を
宅配レンタル<TSUTAYA DISCAS>で借りてみる!/
映画『ファインディング・ニモ』まとめ
映画『ファインディング・ニモ』まとめ(子どもへの「愛情」って何なんだ!)

『ファインディング・ニモ』というタイトルですが、私的には、父・マーリンと子・ニモがメインキャラクターだと感じています。
というのも、「マ―リン」だけ、「ニモ」だけでも決められないように感じました。
相棒のドリーもいて、次作【ファインディング・ドリー】に100歩譲ったとしても、です。
父・マーリンと子・ニモがメインキャラクターだと感じたのは、子・ニモを探しに冒険をしはじめた父・マーリンと相棒・ドリーとの会話のなかででした。
マーリン:「絶対に悪いことは起きないって、なぜわかるんだ」
ドリー:「そんなのわからんない。」
(ドリーの物忘れや何の義理も無い手助け。言動のことは気になりましたけど・・・。)
でもね、やりもしないのに最初から心配する、行動に動かせない・・・これでは身動きできませんよ。
私のことなのですが、いつも言っていることなのです。
「やってみないと分からないじゃないか」「やってみなはれ」
口癖で、放任的な言い方に聴こえるかもしれませんが、いつもこんな感じなんですね。
自分にも周りの人にも・・・です。
だから、これって、これから子どもが欲しい人、今子育てをしている人へのメッセージになるのではないかなぁと思っています。
ほんとうに難しいことなのですけどね。
| ・子ども意見に耳を傾けてみて ・やりたいことをやらせてみて ・子どもにも危険察知を経験させて ・正確な状況判断を身につけさせて ・適切な行動ができるように |
ほかにも、あなたにとって持ち合わせた「テーマ―」って、あるかもしれませんね?
『ファインディング・ニモ』はシンプルだけれども、私たちの社会現実を見事に描写していると思います。
映画『ファインディング・ニモ』エンタメのまとめ
・セルDVD/ブルーレイはこちら
『ファインディング・ニモ』動画が見れるサイトは?
『ファインディング・ニモ』や続編にあたる『ファインディング・ドリー』などピクサー作品は、ディズニー・プラスで、まとめて観られるのでおススメです!
\『ファインディング・ニモ』を
宅配レンタル<TSUTAYA DISCAS>で借りてみる!/
